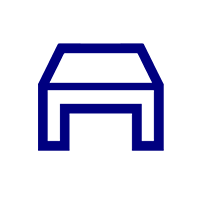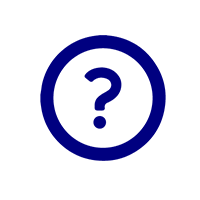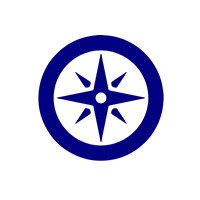1.TSKの「完全レベル別クラス編成」とは何か
「学年別」ではなく「レベル別」ということです。TSKでは、高1生も高2生も等しく「受験生」として扱います。全学年を受験生として捉え、高3生や高卒生だけが受験生ではないという考えです。高1生は3年間、高2生は2年間、高3生・高卒生は1年間受験勉強をしていく「受験生」と捉えています。英語を例にとりますと入会時にクリニックテストを受けてもらい、その結果に従ってクラスを決定していきます。当人のレベルにあった既存のクラスがなければ新たにクラスを新設します。レベルが同じであれば高2生と高3生が一緒のクラスになることもあります。また、授業が進むにつれ、学力レベルが異なってくれば、担当講師と相談の上、クラスを分けていきます。しかも学期毎ではなく学期途中でも、必要ならばクラス分けをしていきます。例えば当初4名クラスだったものが、学期半ばに3名クラスと1名クラス、あるいは2名ずつのクラスに分けるといったようにです。常に生徒達の学力の伸びや理解度をチェックし、それに見合う授業を提供するためです。例えていうなら1対1の完全個別指導クラスがレベルと進路が一致しているので一緒に授業を受けているというイメージで、個別指導の良い点とクラス授業の良い点を融合したものと言えます。
2.成績のアップ・ダウンによるクラス移動は?
大手予備校をはじめとして中小の予備校や塾でも、基本的に入学時以降のクラス移動は想定していないのが普通です。入った時点で、通常クラスや選抜クラスに振り分けられたり、気に入った講師のクラスを選択したりするのが普通で、基本そのクラスのままで受験を迎えます。
それに対してTSKでは、生徒の成績が伸びていくことを前提にクラスを上げていき、テキストのレベルも上げていきます。英語の場合、前述したように入会時に行うクリニックテストや体験授業などでレベル判断を行い、その生徒のレベルから授業を開始していきます。ハイレベルの「Sクラス」から始める生徒もいますが、中学英語や高校初等レベルが不十分な生徒は「一対一の完全個別」から始め、それが終了したら「ステップラダー英語」へ、高校初等レベルの生徒は「ステップラダー英語クラス」から始め、それを終えたら「基礎総合英語クラス」、最後に早慶・マーチや難関国立を目指す「英語Sクラス」というように学力が上がるにつれてクラスやテキストをステップアップしていきます。その判断は、模試の成績や担当講師の評価、土曜演習の成績、そして本人と相談したうえで総合的に行っていきます。テキストは、基礎レベルから上級レベルへの連続性に注意を払って作成しています。
3.なぜ「4名以下のクラス」なのか?
質疑・応答を軸とする「ゼミ式授業を行うための少人数制」であって,単なる人数が少ないだけの少人数制ではありません。
TSKでいうところの「ゼミ式授業」とは、先ず「生徒の疑問に答えていくことを授業の中心に置く授業」ということです。講師の「講義案に沿って授業を進める」のではなく、「生徒の疑問点を軸に授業を組み立てていく」ということです。関係詞ならば、授業を始めるに当たって、受講生の観点から関係詞のどこを重点的に扱って欲しいのか意見を聞いていきます。例えば「関係代名詞と関係副詞との関係が分からない」、「前置詞+関係代名詞での前置詞をどうしたら良いのか」、「関係代名詞の所有格が苦手」、「制限用法と非制限用法が曖昧だ」という意見が出た場合、それらを中心に説明し、全員が分かっている部分は確認程度にして、生徒達とやりとりをしながら理解度を確認しつつ授業を進めていきます。例えば演習の時、間違えたときになぜその答えを選んだのかを説明させ、知識がなかったから間違えたのか、誤った理解をしていたから間違えたのかを確認していきます。また、長文総合問題ならば、長文の段落構成、キーワードやキーセンテンス、設問の意図など生徒に質問し考えながら授業を進めていきます。これは、基礎クラスはもちろん、上級クラスの生徒でも分野によっては基礎レベルの知識が欠けていたり、感覚で何となく解いている場合があるからです。他の予備校ならば、個々の生徒の学力上の穴や弱点を授業内で扱うことは時間的に不可能です。そうしたそれぞれの弱点や疑問や聞きたいところを軸に充実した授業を展開し、対話を通じて生徒の理解度や考え方を確認するためには人数を絞る必要があり、そのために「4名以下のクラス」で、3名クラスもあれば2名クラスや1名クラスもあります。
その結果、自分が疑問に思っていることや聞きたいこと、弱点箇所が授業の中心になるため、授業に対する集中力が生まれ、「理解」が進みます。さらに生徒達からの質問や発言が活発になり、教師と生徒、生徒同士での会話・議論が発生していき、自然と「思考力」や「表現力」が培われていきます。
さらに、レベルを完全に揃え、人数を4名に絞り、生徒の疑問を中心に授業を進めることで、非常に効率の良い授業展開となり、大手予備校の2~3年分の授業量を、濃い授業密度と進度で1年で行っていきます。
このように、TSKの授業は単なる「少人数制」とか「個別指導」あるいは「名ばかりの対話形式」とは異なり、生徒達の「能動的な学習」を促し、「思考力」「判断力」「表現力」を育てるための「授業方式」であり、他では真似の出来ないものだと自負しています。



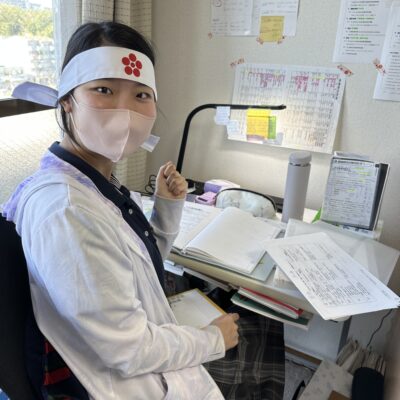
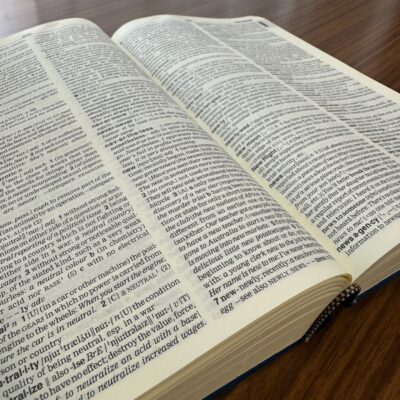

ご家族-400x400.jpeg)